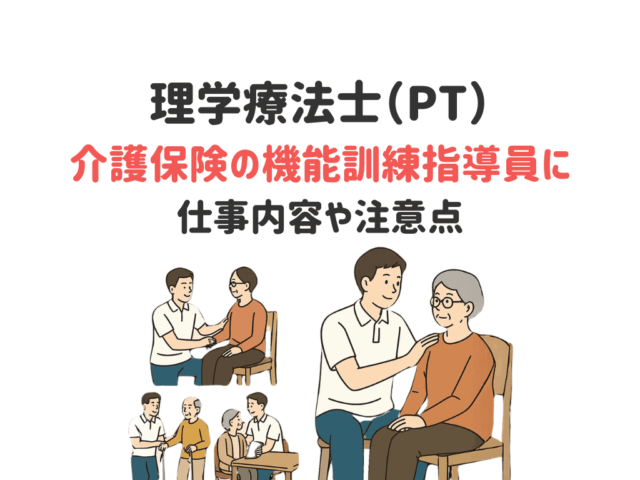柔道整復師が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点

この記事はプロモーションが含まれます。
通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!
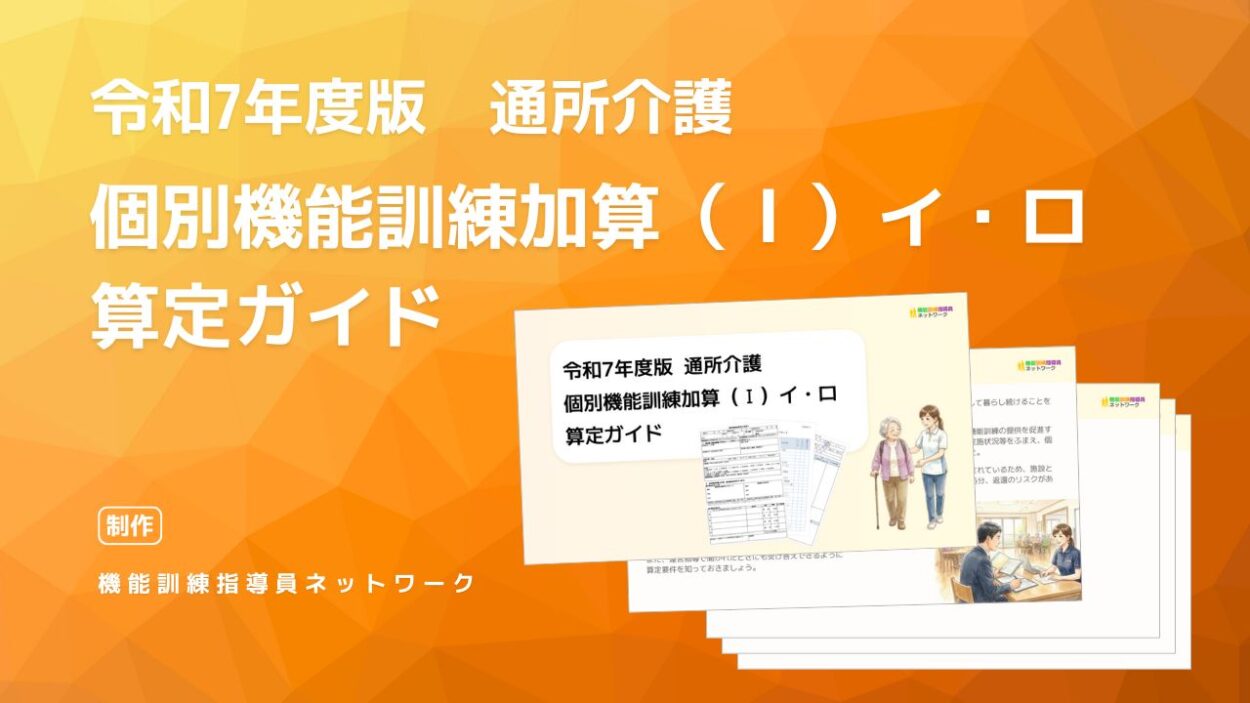
こんなお悩みありませんか?
そんなとき、この教材がお役に立つと思います。
接骨院との違いと、介護現場で求められる視点とは?
柔道整復師の資格を持つ方が、通所介護(デイサービス)などの介護保険施設で「機能訓練指導員」として働く場面が増えています。しかし、接骨院や整骨院での業務と同じ感覚で現場に入ると、制度の壁や目的の違いに戸惑うことも少なくありません。
この記事では、柔道整復師としての専門性と、介護保険における機能訓練の違いを明確にしながら、業務内容と注意点を解説します。
機能訓練指導員の役割と介護保険制度の位置づけ
介護保険制度における「機能訓練指導員」は、身体機能の維持・向上を目指す訓練の計画・実施・評価を担う専門職です。通所介護施設などでは、個別機能訓練加算を算定するために、機能訓練指導員の配置が必要とされます。
この「機能訓練」は、医療行為ではなく、生活機能の維持や自立支援を目的とした非医療的な訓練です。つまり、「痛みを取る」「癒す」ためのマッサージや温熱療法ではなく、日常生活を送る上で必要な動作能力を高めることが目的となります。
接骨院での業務との違い
柔道整復師の主な業務は、外傷や関節の不調に対して整復・固定・後療法を行い、疼痛の軽減や組織の回復を促すことです。そのため、臨床の現場では電気治療や手技療法、テーピングなどを駆使して、患者の「痛みの治療」に集中するのが一般的です。
一方で、介護施設における機能訓練は、「訓練」であって「治療」ではありません。利用者の状態に応じて、立ち上がり動作や歩行練習、階段昇降の指導、福祉用具の使い方の確認など、生活機能の維持・向上を目指した運動プログラムの提供が求められます。
| 項目 | 接骨院での業務 | 介護施設での機能訓練 |
|---|---|---|
| 対象 | 急性外傷などの患者 | 要介護・要支援認定を受けた高齢者 |
| 目的 | 症状の改善、痛みの軽減 | 日常生活動作(ADL)の維持・向上 |
| 方法 | 手技・電療・温熱・固定など | 運動指導・生活動作の練習 |
| 法的根拠 | 柔道整復師法・医療保険 | 介護保険制度 |
| 成果の捉え方 | 治療効果(痛みの消失など) | 自立支援・QOLの向上 |
このように、業務の根拠法・目的・アプローチが大きく異なるため、「接骨院でやっていたことをそのまま持ち込む」のは避けるべきです。
個別機能訓練加算の算定要件とは?
通所介護における機能訓練は、加算制度のもとで算定される「サービス項目」の一つです。主に下記のような加算区分があります。
| 加算名 | 概要 | 実施のための要件 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練を週1回以上行う | 利用者の心身の状況に応じた訓練計画と記録、実施、評価の実施 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | より科学的な訓練計画と評価を含む | ご利用者を評価した内容や計画内容などを国のシステム(科学的介護情報システムLIFE)に提出・フィードバックの活用 |
ここで重要なのが、「痛みを取る」「気持ちよくなってもらう」ための施術だけは基本的には個別機能訓練加算の対象となる訓練には該当しないという点です。以下のような行為は、慰安的・治療的な目的と判断されるため、加算の対象外です。

- マッサージによるリラクゼーション目的のアプローチ
- 温熱や電気療法を用いた疼痛緩和
- 整体的な調整や徒手療法による治療的操作
介護保険制度では、「できないことを減らす」ことよりも、「できることを維持・増やす」という自立支援の考え方がベースとなっています。そのため、日常動作の獲得を目指した訓練であることが前提条件となるのです。
柔道整復師として注意したいポイント
柔道整復師が機能訓練指導員になる際には、以下のような視点を持つことが求められます。
まず一つ目は、「治す」ではなく「支える」という視点の切り替えです。接骨院では患部へのアプローチが中心になりますが、機能訓練では歩行・立位・トイレ動作など、生活全体に関わる運動支援が主となります。
二つ目は、「個別機能訓練計画書」の作成と記録・評価の重要性です。加算を算定するためには、訓練の目的・手段・期間・評価方法を明記した計画書が必須であり、科学的かつ合理的な根拠が求められます。
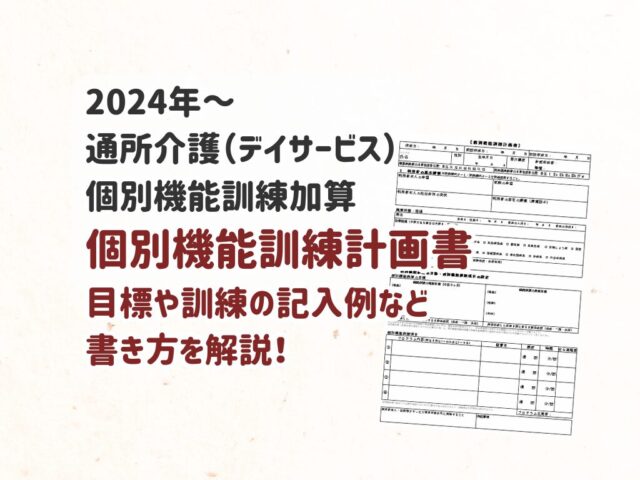
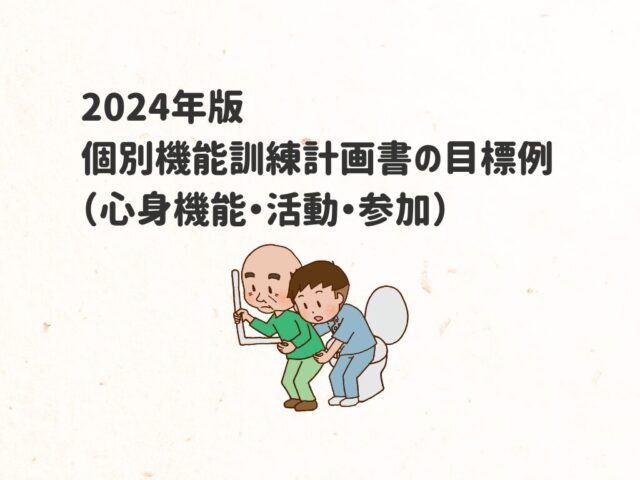
さらに、施設では介護職や看護師、生活相談員、ケアマネジャーとの連携が必要不可欠です。柔道整復師としての視点にこだわりすぎず、チームの一員として協働できる柔軟性も大切な要素になります。
まとめ 柔道整復師だからこそできる機能訓練を、制度に沿って提供しよう
機能訓練指導員は、柔道整復師の知識と経験を活かしながら、高齢者の生活を支える立場として重要な役割を果たします。しかし、介護保険の枠組みの中では、「治療者」ではなく「生活支援の訓練者」として行動する必要があります。
そのためには、以下の3点を意識することがポイントです。
- 制度(介護保険)の目的を理解し、訓練内容を設計すること
- マッサージや疼痛緩和を中心とせず、自立支援を意識した運動を行うこと
- 介護チームの一員として、記録・評価・連携に責任を持つこと
制度への理解を深めることで、柔道整復師ならではの強みを生かしながら、現場で信頼される機能訓練指導員として活躍していくことができるはずです。