機能訓練指導員はやめとけと言われる理由、事例から考える
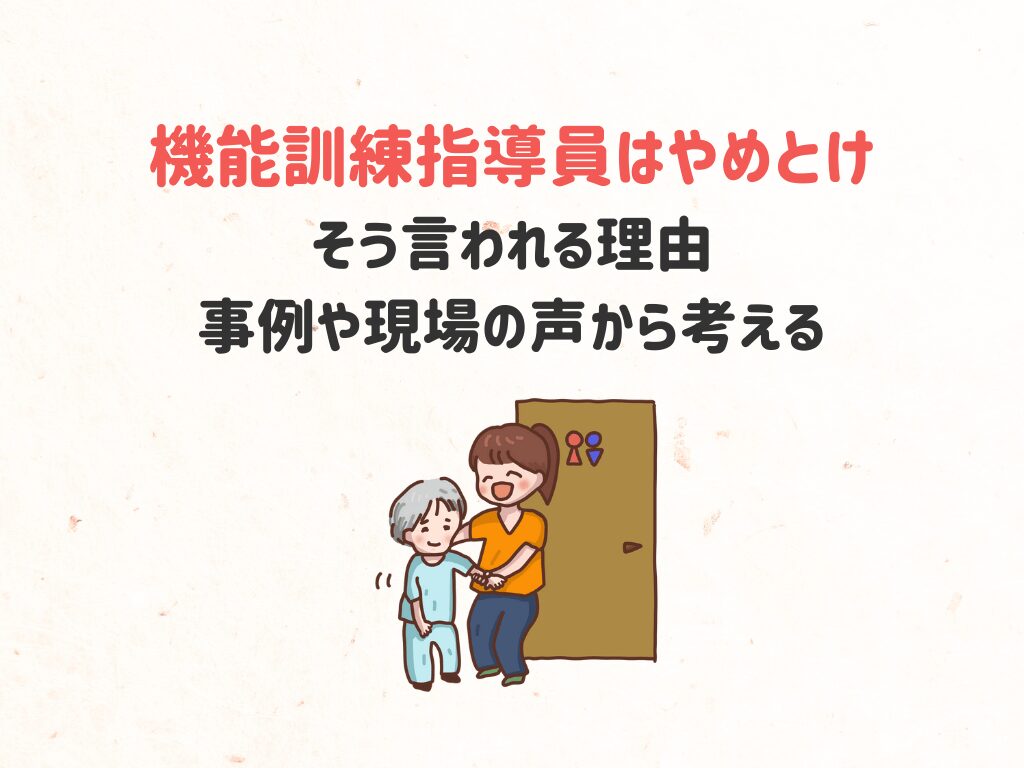
この記事はプロモーションが含まれます。
通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!
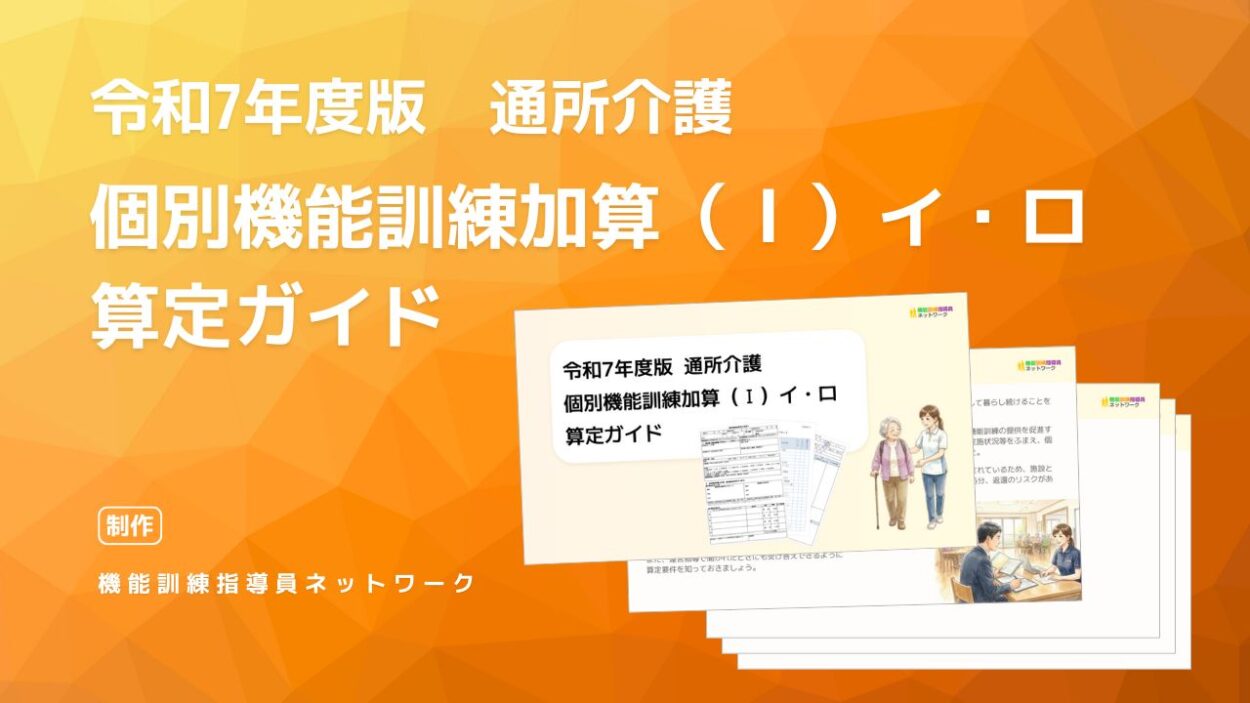
こんなお悩みありませんか?
そんなとき、この教材がお役に立つと思います。
介護業界で一定の需要がある「機能訓練指導員」の仕事。柔道整復師や看護師、理学療法士などの資格があれば就ける職種ですが、ネットでは「やめとけ」といった声も少なくありません。
本記事では、実際の現場経験を踏まえ、「なぜそう言われるのか?」という理由を整理しながら、柔道整復師として機能訓練指導員を目指す際の現実的な視点や心構えをお伝えします。
機能訓練指導員とはどんな仕事か?
機能訓練指導員は、介護施設において高齢者の身体機能の維持・回復を目的とした訓練(リハビリ)を行う専門職です。
主に勤務するのは「通所介護(デイサービス)」と「特別養護老人ホーム(特養)」「有料老人ホーム(特定施設)」など。介護保険制度上、これらの施設には機能訓練指導員の配置が義務付けられており、厚生労働省が定めた要件に沿って計画的に機能訓練を行うことで加算という介護報酬の上乗せがあります。
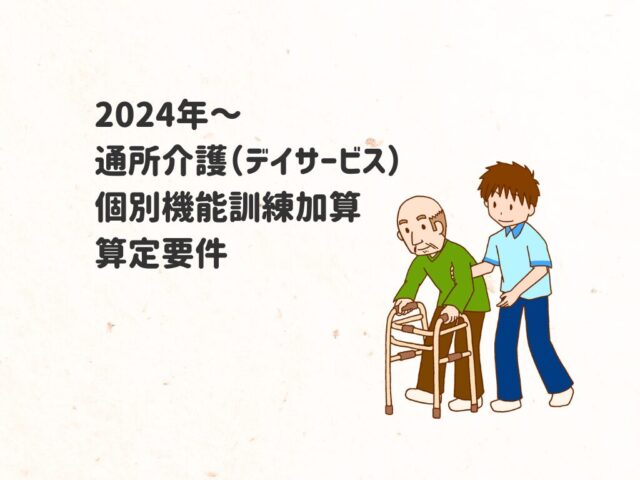


仕事内容の一例(デイサービスの場合)
| 主な業務 | 内容 |
|---|---|
| 個別機能訓練 | 利用者の状態に応じた運動指導、機能維持のための体操など |
| 計画書作成 | 個別機能訓練計画書の作成、評価、見直し |
| モニタリング | 訓練の効果測定、身体状況の記録・報告 |
| 介護補助 | 食事介助、トイレ誘導、レクの補助など |
| 送迎業務 | 利用者の自宅と施設の送迎(助手または運転) |
施設によっては「機能訓練が業務の中心」になる場合もあれば、訓練は短時間で、残りの時間は介護業務や雑務に当てられるケースもあります。
機能訓練指導員は「やめとけ」と言われる理由とその背景
柔道整復師のスキルが活かしにくい
柔道整復師は本来「治療」を行う医療系専門職ですが、介護施設で求められるのは「医療行為ではない」予防的な運動指導や生活リハビリです。機能訓練指導員として働く場合には、個別機能訓練加算という加算を算定するためにその加算の要件に沿った業務を行うことになることが多いですが、治療を行うことは求められておらず、主に生活場面に着目してトイレに行くための動きやお風呂の入り方の練習など、実践的な活動を行っていくことが求められています。柔道整復師やあんまマッサージ指圧師、鍼灸師などの場合には、治療家としての専門性を活かしにくいという点で、物足りなさや戸惑いを感じる人も少なくありません。
理学療法士・作業療法士との待遇差
同じ機能訓練指導員の資格要件を満たす資格として、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)があります。上記で紹介したように、介護保険事業での機能訓練指導員に求められているのは生活を送る上での活動の支援などであり、求人市場ではPT・OTが優先されやすく、待遇にも差が出る傾向があります。施設側としては、国家資格かつ介護施設での経験が豊富なPT・OTを採用したいというニーズも高いのが実情です。
「訓練」以外の業務の多さ
現場の声で最も多いのが、「想像以上に介護の業務が多い」という点です。入浴介助こそ基本的に行いませんが、食事・排泄・送迎・レクリエーション・掃除・記録など、一般的な介護職と変わらない業務も多く含まれます。また、特に機能訓練指導員になりたての時に迷うのが「個別機能訓練計画書」などの作成に関することです。
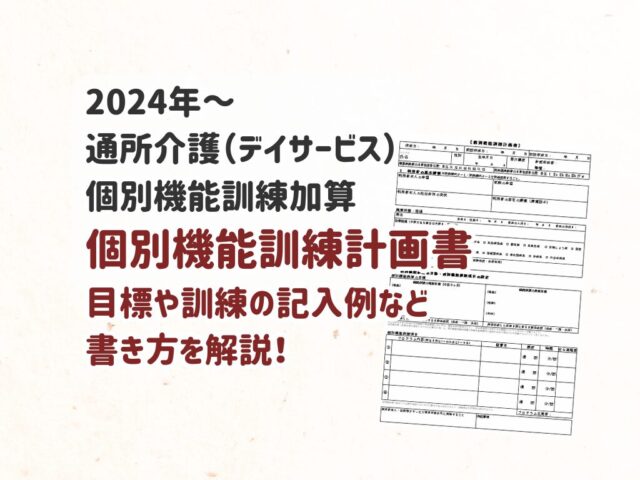
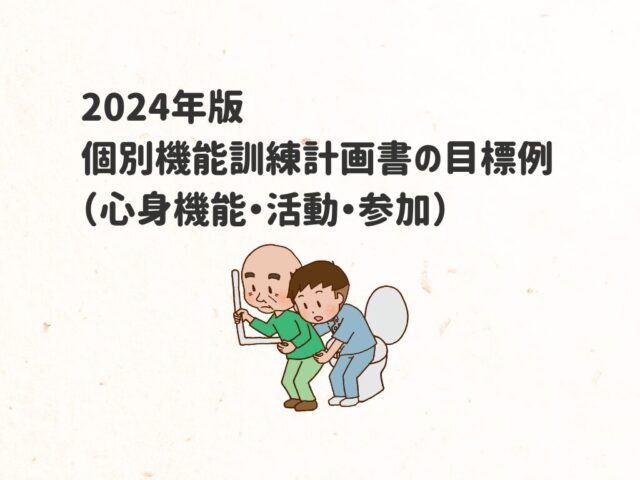
機能訓練を行う時には、個別的で計画的に、そして痛みを取ることや慰安目的という行為でなく、ケアマネジャーの作成してるケアプランを確認し、ご利用者が生活上で困っている動きや必要な活動などを確認した上で計画を立てなければなりません。ただ単にマッサージをしたりもみもみしているだけの機能訓練指導員は介護保険事業の中では価値が低く、介護保険の制度で定められた業務と、組織の中でみんなで行わなければならない業務を周りを見ながら行える人が求められます。
参考:ケアプラン・ケアマネジャー業務について(介護健康福祉のお役立ち通信)
施設ごとの差が大きく、ブラック施設も存在する
とくに注意すべきなのが、施設ごとの労働環境の差が非常に大きいという点です。例えば、「お泊まりデイサービス」のように夜勤を求められるケースや、無資格のまま送迎・介助を過度に任せられるなど、ブラックな運営をしている施設も存在します。
柔道整復師の機能訓練指導員としての将来性
「リハビリ=PT/OT」という認識が強まる中、柔道整復師が機能訓練指導員として働くことに将来性はあるのでしょうか?
実際には、次のような視点でのニーズが一定数あります。
- 柔道整復師は人件費が安く、雇用しやすい
- 手技によるリラクゼーション要素(癒し)を期待されている
- 地域密着の小規模施設では、柔道整復師に任せきりになるケースもある
つまり、「治療家」としてのスキルよりも、「介護現場にフィットする柔軟さ」「マルチな役割を果たす力」が問われる立場です。スキルよりも、コミュニケーション力・チームワーク・柔軟性が評価される傾向があります。
未経験・年齢が高くても就職できるのか?
年齢や経験の有無は、施設ごとに基準が異なります。
- 都心部や人気エリアでは経験者の応募が殺到し、採用は狭き門
- 一方で、地方や人手不足の施設では未経験でも歓迎されやすい
- 介護保険の仕組みや個別機能訓練加算のルールを理解していると重宝される
柔道整復師という国家資格があれば、「資格者枠」としての採用は可能ですが、採用後すぐに戦力になることが求められるため、最低限の介護知識と現場対応力があると安心されやすいでしょう。
就職先の選び方とブラック施設の見分け方
悪質な施設に就職しないためには、以下のような視点で事前チェックすることが大切です。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 勤務時間・夜勤の有無 | 「お泊まりデイサービス」や夜勤体制の有無を確認 |
| 業務内容の明記 | 面接時に「訓練以外の業務」の割合を確認 |
| 離職率 | 職員の定着率が低い施設は注意が必要 |
| 男性職員の在籍状況 | 男性一人だと人間関係に悩むケースもあるため確認推奨 |
| 福利厚生・労働条件 | 社保完備、有給取得率、研修体制の有無などを要確認 |
初めての就職先は、可能であれば大手法人や実績のある運営母体を選ぶと安心です。個人経営や規模の小さい事業者は、運営方針や責任の所在が不安定なこともあります。
働くうえで大切な心構え
最後に、機能訓練指導員として介護の現場に入る際に持っておきたい姿勢をまとめます。
- 利用者は「患者」ではなく「お客様」
- 一人ひとりの生活を支える「サービス業」であるという意識
- 治療よりも「予防」や「維持」の発想が求められる
- 他職種との協働を大切にし、臨機応変な動きができる柔軟さ
多くの現場では、「この利用者にはこういう運動がいいのでは?」「この声かけが効果的かもしれない」といった提案力が重視されます。経験を積みながら、信頼される存在を目指していくことが何より大切です。
やめとけ、という声の裏にある「覚悟」
「機能訓練指導員はやめとけ」と言われる背景には、介護と医療のギャップ、待遇の問題、職務の多様さがあります。しかし一方で、やりがいを感じて長く続けている方も多く、向き不向きと覚悟次第という面も大きい仕事です。また、高齢者分野で働く上では覚悟しなくてはいけないこととして、日本の社会構造上、高齢者人口が「減り始める」のは2040年頃と言われていますので、それ以降はより高齢者を対象にした事業は厳しくなることが予想されます。また、その頃には高齢者に機能訓練を提供するということ自体が時代や制度にマッチしていない状態になっている可能性もあります。
| 年 | 高齢者人口(65歳以上) | 備考 |
|---|---|---|
| 2020年 | 約3,618万人 | ピークに近づきつつある |
| 2030年 | 約3,716万人 | 横ばいに近い増加 |
| 2040年 | 約3,668万人 | このあたりから減少が始まる |
| 2050年 | 約3,467万人 | 本格的な減少期へ |
| 2060年 | 約3,191万人 | 減少が続く |
機能訓練指導員としてとして、地域の高齢者を支え、チームの一員として現場を動かす。その意味を理解し、自分なりの役割を見出すことができれば、決して悪い選択ではないはずです。

