作業療法士(OT)が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点
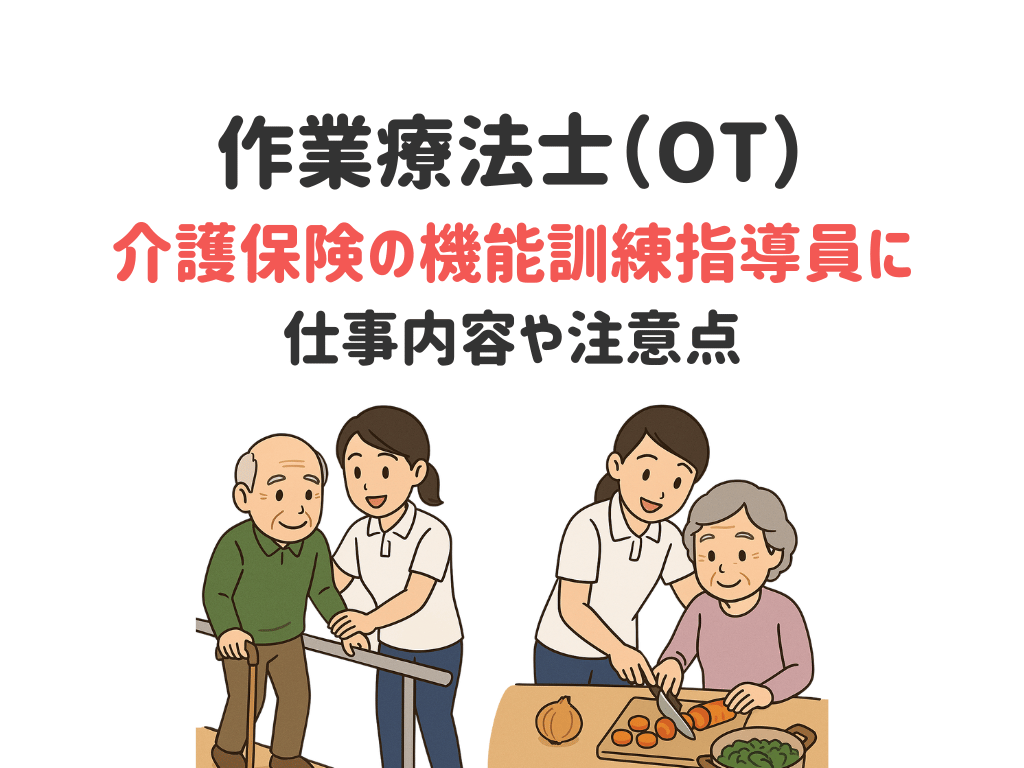
この記事はプロモーションが含まれます。
通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!
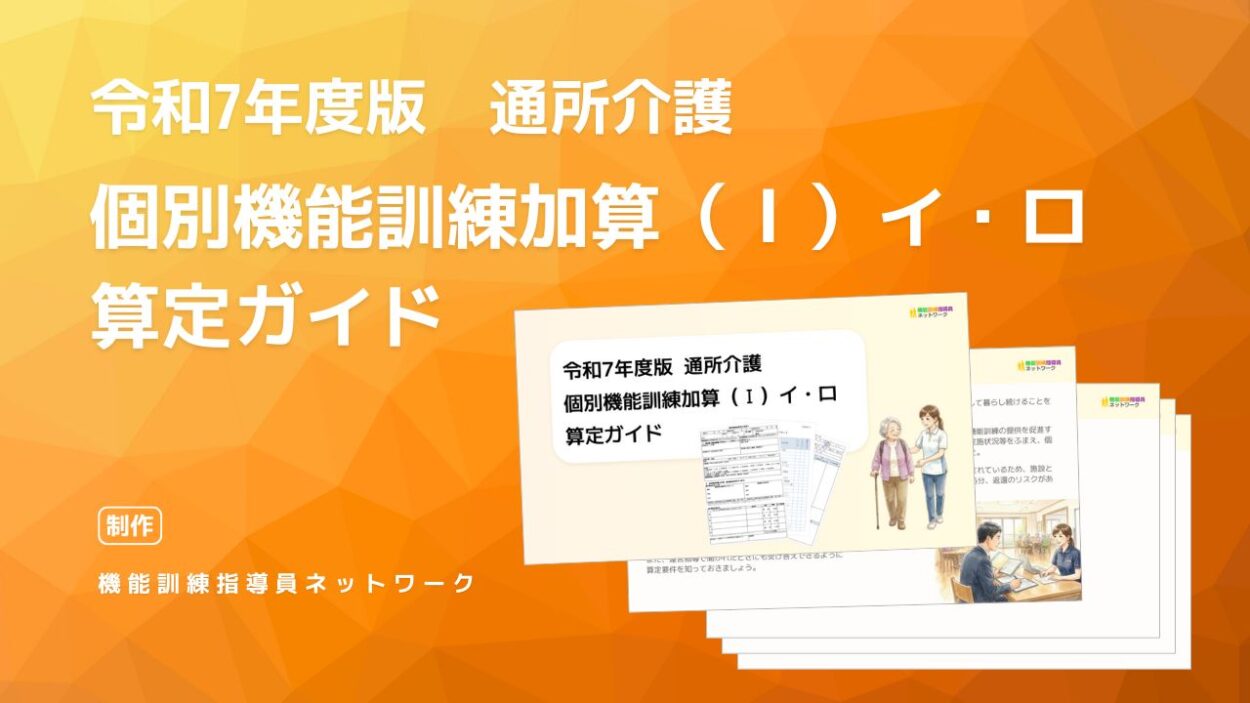
こんなお悩みありませんか?
そんなとき、この教材がお役に立つと思います。
病院との違いと、生活機能の専門家としての役割とは?
作業療法士(Occupational Therapist:OT)の国家資格を持つ方が、介護保険施設、特に通所介護(デイサービス)で「機能訓練指導員」として働くケースが増えています。しかし、病院など医療リハビリの現場での経験だけでは、介護保険制度における機能訓練との違いや、役割への理解が不十分なこともあります。
この記事では、介護保険制度における機能訓練の目的と算定要件に基づき、作業療法士の専門性がどう活かされるのか、どのような点に注意が必要かを詳しく解説します。
医療リハビリとの違い、「治療」から「生活支援」へ
医療機関で働く作業療法士の役割は、ADL(日常生活動作)訓練や、上肢機能の回復、認知機能の維持などを通じて、患者の退院後の生活を見据えた「機能の回復」を支援することにあります。多くの病院では、理学療法士(PT)と業務が重なりやすく、実際には「歩行訓練の補助」「関節可動域の拡大」など、理学療法的なリハビリに従事している場面も少なくありません。
一方、介護保険施設における機能訓練では、目的そのものが大きく異なります。介護保険の機能訓練は「治す」ためではなく、「今の生活をできる限り長く維持し、自立した生活を送ること」を目的としています。つまり、作業療法士が本来持っている「生活に結びついた動作の改善と支援」の専門性が、そのまま活かせる環境だといえます。
介護施設での機能訓練と、医療機関での作業療法の違い
| 項目 | 医療機関(病院・クリニック等) | 介護保険施設(通所介護等) |
|---|---|---|
| 主目的 | 機能回復・治療 | 自立支援・生活機能の維持 |
| 対象者 | 発症直後や術後の患者など | 要支援・要介護の高齢者 |
| 訓練内容 | 上肢機能訓練、ADL練習、認知リハなど | トイレ動作、更衣、調理練習、買い物練習など |
| 評価方法 | 可動域、筋力、認知評価スコアなど | 生活機能チェック、QOLの変化、ADLの継続度など |
| 保険制度 | 医療保険 | 介護保険(個別機能訓練加算) |
このように、「生活に即した訓練」こそが、介護現場での作業療法士の強みになります。特に、個別機能訓練加算の制度は、利用者一人ひとりの生活背景や希望に応じた訓練計画の策定と、計画的な支援を評価する仕組みとなっており、生活活動の専門家であるOTの視点が極めて重要です。
個別機能訓練加算と作業療法士の役割
介護施設で機能訓練指導員が関わるうえで基盤となるのが、個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ)です。
この加算は、単に運動機能を改善するのではなく、利用者の生活機能の向上とQOL(生活の質)向上を目的とした訓練に対して報酬が認められる制度です。
| 加算名 | 概要 | 実施のための要件 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練を週1回以上行う | 利用者の心身の状況に応じた訓練計画と記録、実施、評価の実施 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | より科学的な訓練計画と評価を含む | ご利用者を評価した内容や計画内容などを国のシステム(科学的介護情報システムLIFE)に提出・フィードバックの活用 |
特に重要なのは、「関節可動域の拡大」や「痛みの軽減」だけでは原則加算の対象とはならないという点です。訓練内容が利用者の生活課題と明確に結びついているかが、加算の可否を左右します。
たとえば、買い物かごを持つための肩の運動や、食器を並べるための手指の練習、あるいは外出に備えた財布の出し入れ練習など、日常生活上の動作に即した訓練であることが重要です。
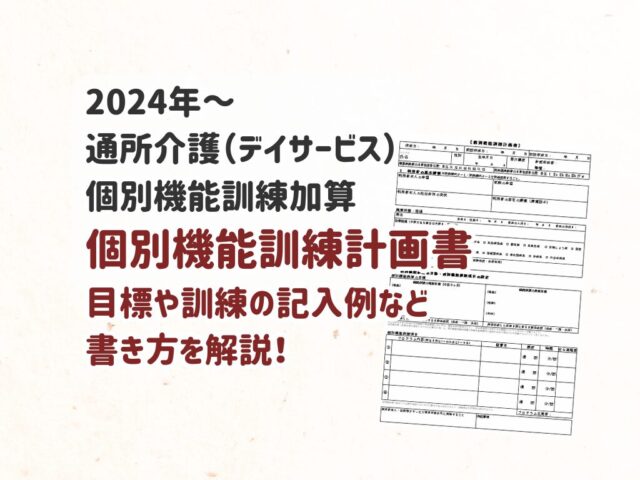
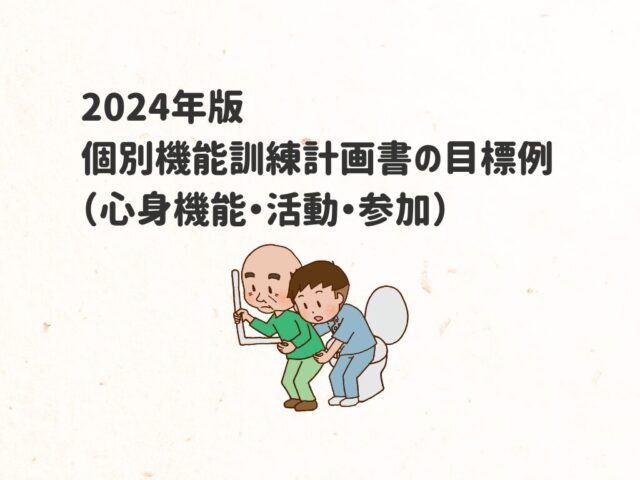
OTだからこそできる機能訓練とは?
介護保険制度のもとで機能訓練を行う場合、作業療法士はまさにその「本領」を発揮できる職種です。身体機能を評価するだけでなく、「この利用者がどんな生活を送りたいのか」「どこに生活課題があるのか」を見抜き、必要な動作を段階的に支援していくことがOTの真価です。
病院ではどうしても理学療法士と同様の役割が求められることもあり、「作業療法士らしさ」が見えにくい場面もあります。しかし、介護施設では、「調理」「掃除」「金銭管理」「買い物」などのIADLや社会参加といった、より生活に近い活動を扱えるため、OTとしての専門性が直接的に評価されやすい環境と言えるでしょう。
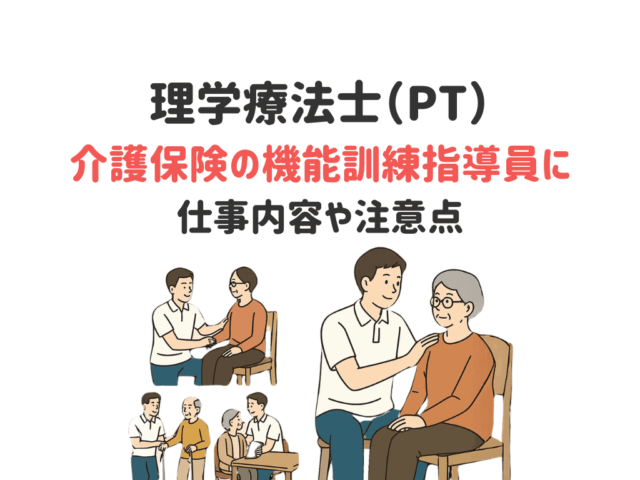
注意すべき点と実務上の心得
作業療法士が機能訓練指導員として働く際には、個別機能訓練加算の算定要件に沿った評価・計画作成、訓練の記録と根拠の明確化が重要です。加算算定の対象である以上、「なぜこの訓練が必要なのか」「どのような生活課題を解決するためなのか」「目標に対して効果が出ているか」といったPDCAの視点で、記録に残すことが不可欠です。
また、医療的な「訓練者」としてではなく、介護チームの一員として連携する姿勢も重要になります。介護職員や看護職員、生活相談員、ケアマネジャーなど、多職種と連携しながら、利用者にとって最善の支援を考えていく柔軟さが求められます。
まとめ OTは「介護の現場」でこそ専門性を発揮できる
作業療法士が介護施設で機能訓練指導員として働くことは、病院でのリハビリとは違った責任とやりがいがあります。介護保険制度の中では、生活機能の維持・向上という明確な目標のもとに、OTが培ってきた「生活を見る力」が真に求められるのです。
とくに以下の3点を意識することが、介護現場での活躍につながります。
- 治療的アプローチではなく、「生活上の動作改善」を軸にした訓練を行うこと
- 個別機能訓練加算の算定要件に沿った計画作成と記録を徹底すること
- 作業療法士らしい生活支援の視点をもって、多職種と協働すること
病院でのOT業務に物足りなさを感じている方にこそ、介護の現場でこそ真の作業療法が実践できるという視点で、新たなフィールドに挑戦してほしいと願っています。
