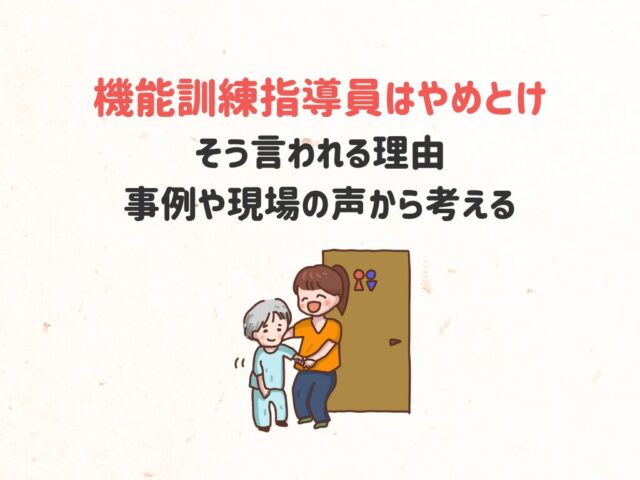看護職員(看護師・准看護師)が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点

この記事はプロモーションが含まれます。
通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!
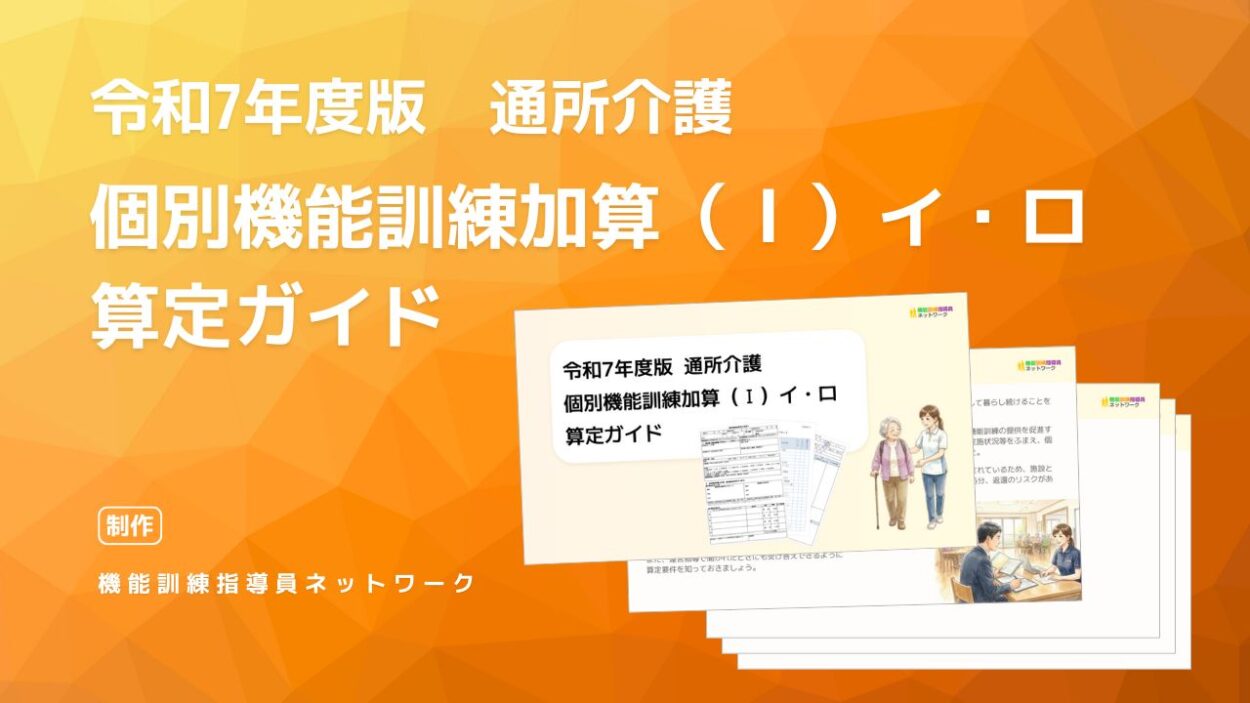
こんなお悩みありませんか?
そんなとき、この教材がお役に立つと思います。
介護業界では、看護職員(看護師・准看護師)が「機能訓練指導員」としても働くケースが増えています。看護のスキルを活かしながら高齢者の身体機能維持に関わることができ、やりがいもある職種ですが、実際には看護職との違いや兼務時の注意点、介護保険制度のルールを理解しておく必要があります。
この記事では、看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に知っておきたい基礎知識を、厚生労働省のQ&Aに基づいて正確に解説します。
看護職員と機能訓練指導員の仕事内容の違い
まずは、看護職員と機能訓練指導員の基本的な業務の違いを確認しましょう。
| 項目 | 看護職員 | 機能訓練指導員 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 健康管理・医療的処置・服薬管理 | 身体機能・活動・社会参加の維持・回復を目的とした訓練 |
| 主な業務内容 | バイタルチェック、服薬管理、処置、観察記録など | 個別機能訓練の計画・実施・記録、評価、身体状況のアセスメントなど |
| 利用者との関わり | 日常の健康維持を中心にした支援 | 運動・動作・活動・交流の促進による自立支援 |
| 保険制度上の扱い | 医療的支援(介護施設における看護配置義務あり) | 介護保険上の機能訓練加算の算定対象 |
どちらも「利用者の健康を支える」点では共通していますが、役割の焦点が異なることに留意が必要です。
看護職員が機能訓練指導員を兼務することはできる?
一定条件下で兼務は可能
厚生労働省のQ&Aでは、看護職員が機能訓練指導員を兼務することは原則として認められています。ただし、その勤務形態や施設の規模に応じて注意点が異なるため、施設種別ごとに整理してみましょう。
施設種別ごとの兼務ルールと注意点(厚労省Q&Aより)
通所介護・地域密着型通所介護(定員11名以上)
- 兼務は可能
- 看護職としての業務に従事していない時間帯に限り機能訓練指導員として勤務可能
- 看護職・機能訓練指導員いずれも「配置時間の規定はなし」
- 実際の勤務内容と記録により、役割の区別ができるようにしておく必要あり
地域密着型通所介護(定員10名以下)
- 兼務は可能
- 「看護職員または介護職員」の配置基準を看護職員で満たしている場合に限り、看護業務以外の時間に機能訓練指導員として従事可能
- 機能訓練指導員としての時間は、看護職の時間には含めないので管理に注意
認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
- 兼務は可能
- 配置基準(a:1名以上配置、b:勤務時間の合計数÷提供時間数で1以上)を満たすことが前提
- 機能訓練指導員としての時間は、看護職員としての配置時間には含まれない
実務での注意点 こんなところに気をつけよう
役割の明確化と時間管理
たとえ一人の職員が両方の業務を行うとしても、「どの時間に何をしていたか」を記録上で明確にしておくことが重要です。看護職員としての業務に就いていない時間帯に機能訓練を行うよう、スケジュールや記録簿の工夫が求められます。時間管理については業務を効率的に行うという点でも重要ですが、看護職員と機能訓練指導員を兼務している場合には両方の業務に支障がないように時間を区分して行っているということが分かるような形にしておかないと運営上問題がありますので、管理者としっかりと相談して気をつけていきましょう。
利用者への説明と対応力
利用者やご家族は、「看護師がやってくれるから安心」と期待している場合もあります。しかし、機能訓練指導員の業務は医療行為ではありません。治療と訓練の違いを理解し、適切に説明・対応できる力も必要です。
ケアマネ・他職種との連携
機能訓練はケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて行います。他職種(介護職、リハ職、ケアマネ等)との連携を密に取り、計画的に訓練を実施することが重要です。
過重労働にならないようにする
小規模な施設では、「人手が足りないから両方お願い」とされることもあります。看護業務と機能訓練業務はどちらも責任が重いため、労働時間や業務負担のバランスに配慮しましょう。
看護師が機能訓練指導員として働くメリット
看護師が機能訓練指導員を兼務することには、次のようなメリットもあります。
- 看護スキルを活かしつつ、介護予防・リハビリ分野に関われる
- 高齢者のQOL向上に直接貢献できる
- 通所介護などで日勤・土日休みが中心となり、働きやすい環境
また、看護師は機能訓練指導員として正式に配置基準を満たす資格職種の一つであり、医療と介護の橋渡し役としても高く評価されています。看護師が機能訓練指導員を兼務するということはとても価値の高いことですので、そのことを評価せずやって当たり前というような態度をとってくるような経営者には気をつけましょう。
まとめ 看護師×機能訓練指導員は両立可能、ただし制度と現場の理解がカギ
看護師・准看護師が機能訓練指導員としても働くことは、制度上明確に認められています。
ただし、時間帯・業務内容・記録管理・役割の切り分けに注意しなければ、制度違反となる可能性もあります。
また、利用者にとっても「健康管理のプロがリハビリをしてくれる」という安心感は大きなもの。介護と医療の両面から高齢者を支えることができる存在として、やりがいも高い働き方です。
重要なのは…
- 制度のルールを理解し、兼務可能な範囲を明確にする
- 記録・業務分担を施設内で共有する
- 過重労働を避け、現場と適切に調整する
看護師として健康面の相談に乗ったり医療的な面のケアで支えたりすることに加えて、生活上の困りごとなどに対しても支援ができる機能訓練指導員という役割は、ご利用者に喜んでもらえる仕事の一つです。一方で、個別機能訓練加算を算定する事業所での機能訓練指導員として働く場合には、個別機能訓練加算の算定要件を満たすための事務手続きや書類作成などが必要になります。機能訓練指導員はご利用者にサービス提供をしつつ事務的な部分もこなしていかなくてはならないという負担の大きい業務になりますので、バランスを取りながら無理なく働いていけると良いでしょう。
看護師の転職・働き方については、医療キャリアナビの記事も参考になります。(参考:医療キャリアナビの記事)