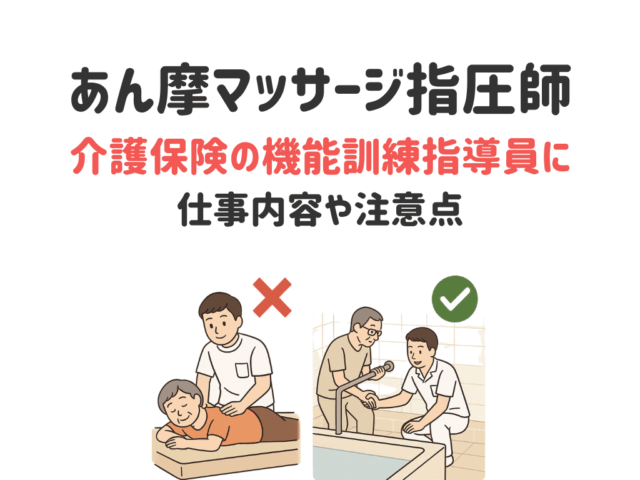言語聴覚士(ST)が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点
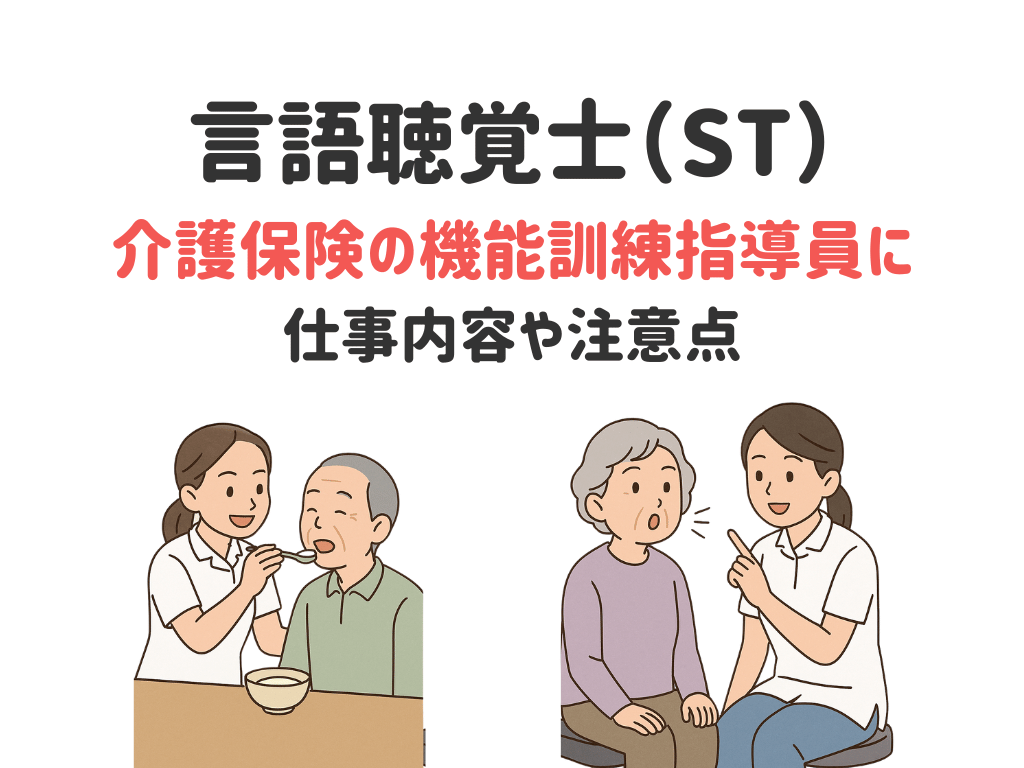
この記事はプロモーションが含まれます。
通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!
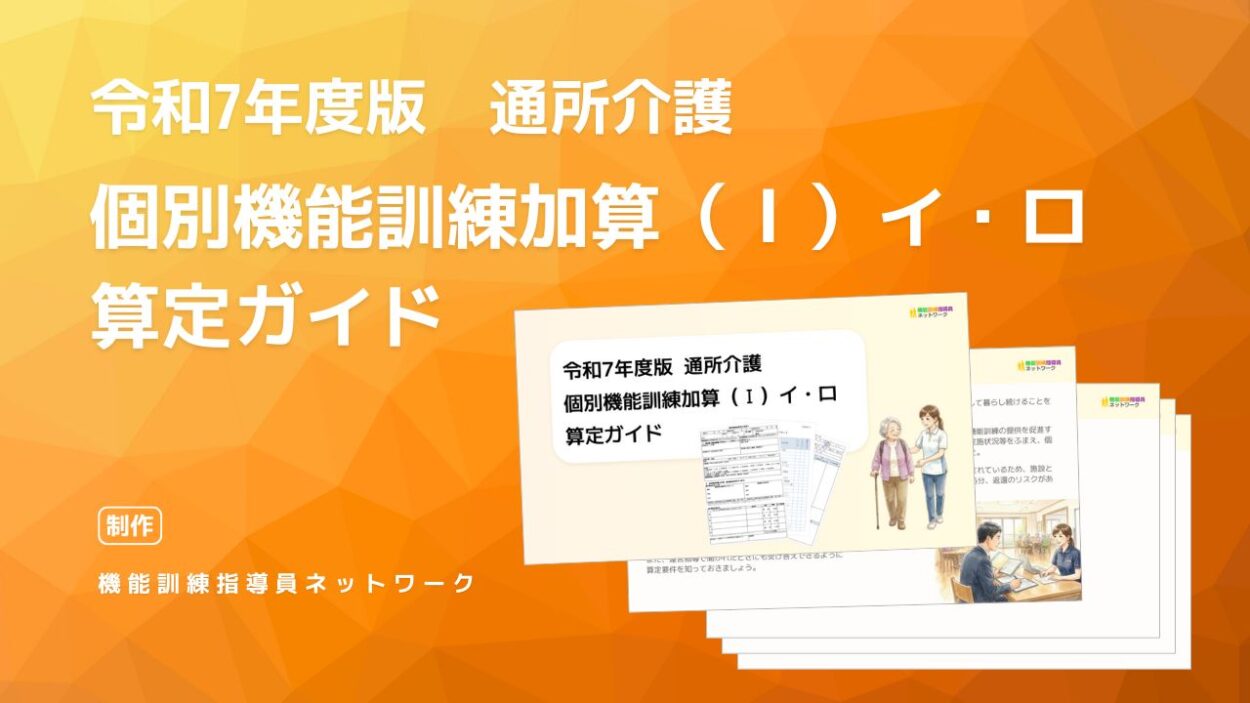
こんなお悩みありませんか?
そんなとき、この教材がお役に立つと思います。
言語や聴覚、飲み込み(嚥下)など、生活の根幹を支えるリハビリテーションを専門とする国家資格「言語聴覚士(ST)」。これまで主に病院やクリニックのリハビリテーション科で活躍してきたこの専門職が、近年では介護保険施設において「機能訓練指導員」としての活躍の場を広げています。
しかし、医療現場でのリハビリと、介護保険制度に基づく機能訓練とでは、目的や手法、求められる視点が大きく異なります。本記事では、言語聴覚士が通所介護などで機能訓練指導員として働く際に知っておきたい仕事内容や注意点、個別機能訓練加算との関係性、医療と介護の現場の違いについて、制度的な根拠も交えて詳しく解説します。
言語聴覚士(ST)とはどんな資格か
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)は、国家資格を持つリハビリテーション専門職で、言語や聴覚、嚥下(飲み込み)などの障害に対して評価と訓練を行います。
主な対象となるのは、脳卒中後の失語症や構音障害、認知症によるコミュニケーション障害、摂食嚥下障害、難聴などで、「話す・聞く・食べる・飲み込む」といった生活の根幹を支える機能を扱う専門職です。
医療機関では、急性期・回復期の患者に対して、リハビリテーション科に所属し、医師の指示のもとでリスクを伴う嚥下訓練や聴覚評価、訓練、言語訓練などを中心に業務を行います。
近年ではこの専門性が、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームといった介護保険施設においても必要とされるようになってきました。その際、重要な役割となるのが「機能訓練指導員」としての業務です。
医療機関と介護施設におけるSTの業務の違い
病院でのST業務と、介護施設での機能訓練指導員としてのST業務は、一見似ているようで制度的な役割や業務内容が大きく異なります。
| 項目 | 医療機関におけるSTの業務 | 介護施設におけるSTの業務(機能訓練指導員) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 医学的回復、病態改善、合併症予防 | 自立支援、生活機能の維持・向上 |
| 評価・診断 | 医師の指示に基づいた検査や診断 | 医師の診断は不要、生活課題に基づくアセスメント中心 |
| 保険制度 | 医療保険(診療報酬) | 介護保険(個別機能訓練加算) |
| 業務内容 | 嚥下評価・VF/VE対応、言語訓練、聴覚訓練など | 食事動作や構音、認知の支援・訓練、生活支援に必要な訓練全般 |
| リスク対応 | 医療体制が整っている | 医療対応が限定されており、リスク管理が重要 |
このように、介護保険制度のもとでは、「治療」ではなく「生活機能支援」のための訓練であることを理解し、制度のルールに則ったアプローチをとる必要があります。
個別機能訓練加算の制度とSTの関わり
介護施設における「機能訓練指導員」は、個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定に必要な職種の一つです。この加算は、利用者の心身の特性に応じた自立支援や生活機能の維持・向上を目的とした訓練を行うことで、施設に対して介護報酬として支払われる制度です。
| 加算名 | 概要 | 実施のための要件 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練を週1回以上行う | 利用者の心身の状況に応じた訓練計画と記録、実施、評価の実施 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | より科学的な訓練計画と評価を含む | ご利用者を評価した内容や計画内容などを国のシステム(科学的介護情報システムLIFE)に提出・フィードバックの活用 |
言語や構音、嚥下などの訓練は、利用者の「話す・食べる」といった生活機能に直結するため、加算の目的に合致する内容です。特にSTは、口腔機能向上加算や栄養改善加算などとの連動でも重要な役割を果たすことができます。
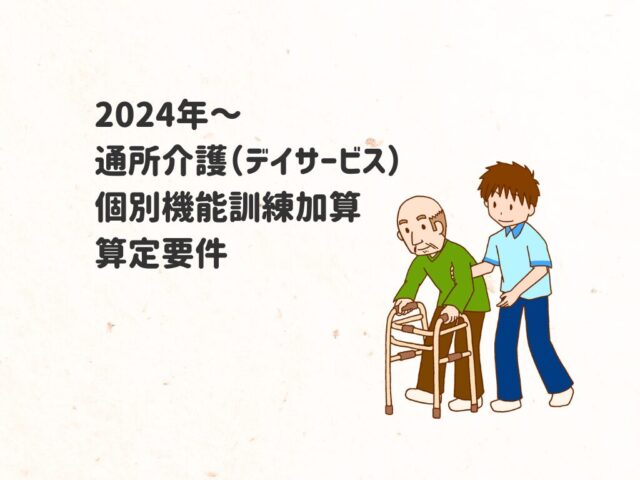
STとして活かせる訓練内容と実務のポイント
言語聴覚士が介護施設で活躍する場面は多岐にわたります。以下のような訓練は、個別機能訓練加算の目的に合致しており、生活機能の支援として評価されます。
- 嚥下訓練・食事動作の支援:食べる、飲み込む機能を維持し、誤嚥予防・栄養状態の改善を図る
- 口腔体操・発声訓練:構音の明瞭化、発語の維持、社会参加を促す
- 会話訓練・認知的刺激:認知症予防やコミュニケーション機会の確保
ただし注意点として、介護施設では医療機関ほどの緊急対応力がないため、特に嚥下訓練においては誤嚥や窒息といったリスクへの十分な配慮が必要です。事業所が許容できるリスクをあらかじめ確認しておき、訓練中に急変が起きた場合の対応や、どの程度まで踏み込んだ訓練をするかなどについても施設全体で決め、家族やケアマネジャーにも十分な説明をしておきましょう。
また、介護施設で嚥下評価が必要な場合には、医療機関や歯科医師との連携、ケアマネジャーへの報告・協働を行い、支援計画に反映していくことも大切です。
身体的機能訓練への対応力も求められることがある
通所介護施設では、STの専門性である「言語・嚥下」に関するニーズを持たない利用者も多くいます。そうした場合、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が担当するような身体機能訓練や日常動作練習を、STが補うケースも出てきます。
特に施設の人員体制や加算取得状況に応じて、基本動作訓練や認知機能支援、ADL向上支援などを包括的に行う必要があるため、STとしての専門性に加えて多角的な支援スキルと柔軟な対応力が求められるでしょう。
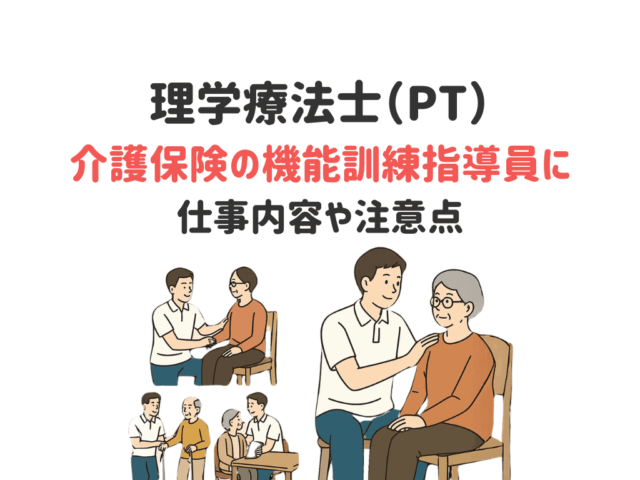
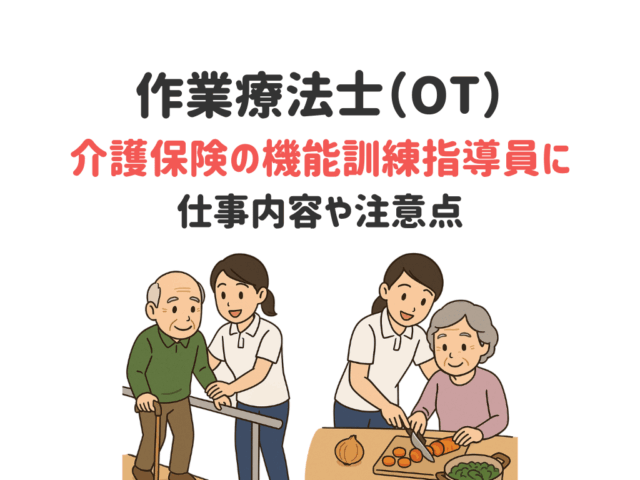
言語聴覚士の希少価値は介護施設のブランディングにも役立つ
言語聴覚士の専門分野である、「話す・食べる・聞く・コミュニケーションをとる」ということは、要介護者にとってニーズが高い分野です。それゆえに、できるだけ話ができるようになりたい、少しでも食べ物を味わいたいなど、ご利用者が望む生活の中で優先度が高いニーズに対しての具体的なサービスが提供できるのが言語聴覚士の強みです。
介護老人保健施設などには言語聴覚士が配置されている施設もありますが、介護施設の中で言語聴覚士が在籍しているという事業所は少ないので、施設の特色として言語聴覚士がいるということは非常に強い存在です。施設の営業目的で言語聴覚士がいるということを使われてしまう部分もありますが、期待に応えていくことでキャリアも経験も積めるのが、介護保険分野での機能訓練指導員の仕事だと思います。
まとめ STの専門性は介護施設でこそ活かせる
言語聴覚士は、「話す・食べる・伝える」ことに専門性を持った職種です。
この専門性は、介護施設においても生活の質(QOL)を高めるうえで非常に重要な役割を果たします。特に個別機能訓練加算の制度的な枠組みにおいては、STの訓練内容がそのまま対象となるケースが多く、介護現場でも評価されやすい職種といえるでしょう。
一方で、医療機関とは異なるリスク体制の中で訓練を行う必要があるため、安全管理や医療連携の意識を持つことが欠かせません。加えて、身体面の支援や記録作成、他職種との情報共有といった多面的な役割にも柔軟に対応していく姿勢が求められます。
STの知識とスキルを、単なる医療的「治療」ではなく、「生活機能を支える支援」として活かすことで、介護施設におけるより良い支援が実現できます。